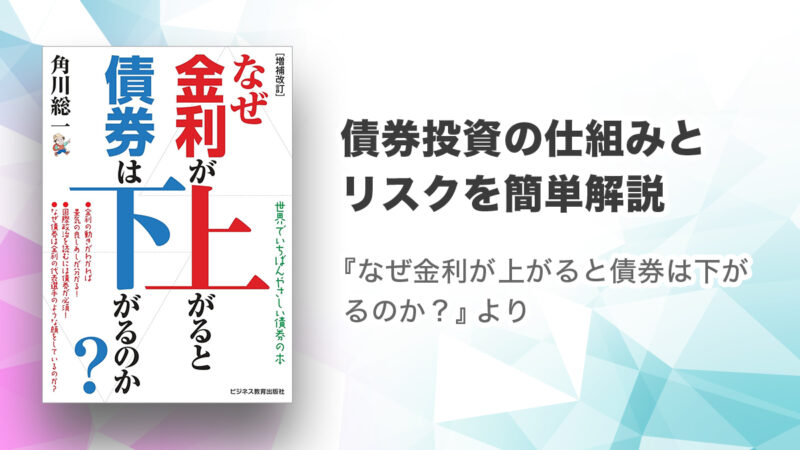「債券って難しそう」「株式や為替は価格で動きが分かるのに、債券は利回りで示されるから直感的に理解しにくい」「価格がどう変動するのかも分かりづらい」。こう感じる方は少なくないでしょう。債券は、日々ニュースで報道される日経平均株価などと比べて情報が少なく、また、株式や為替のように単純な価格の動きだけでなく、利回りの計算も必要になるため、仕組みが複雑に思えるかもしれません。さらに、個人投資家にとってはあまり身近な資産運用手段ではないため、「なんだか面倒そう」と漠然としたイメージを持たれている方もいるでしょう。
しかし、これからの連載を読み進めることで、「なるほど、そういうことだったのか!」と納得できるはずです。債券がぐっと身近に感じられるようになるでしょう。
本記事では、債券の仕組みとそのリスクについて解説していきます。
今回のテーマは、「債券のゆりかごから墓場まで」です。
債券を理解する上で参考になる書籍として、『なぜ金利が上がると債券は下がるのか?』をご紹介します。
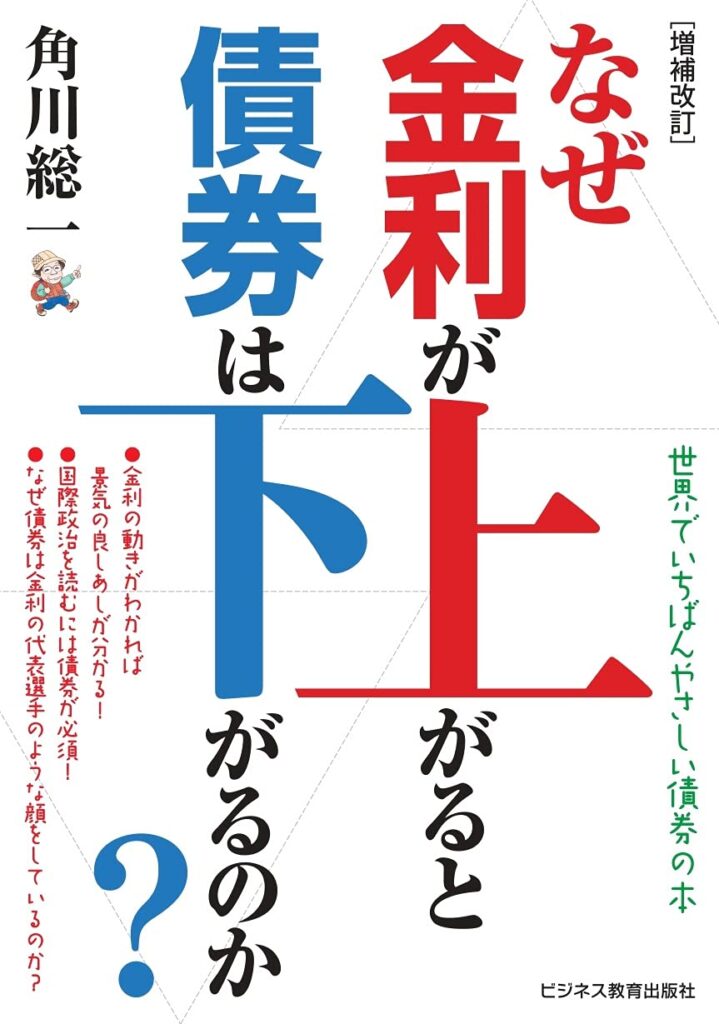
債券とは何か?
まず、債券とは「国や企業などが資金を調達するために発行する借用証書のようなもの」です。債券を購入した人は、定期的に利息を受け取り、満期が来ると元本が返還されます。特に、日本における国債の発行残高は2020年12月時点で約1200兆円に達しており、株式の発行額を大きく上回る規模となっています。
預金とは何が違うのか?
債券の本質を理解するには、「預金とどのように異なるのか」という視点で見ると分かりやすくなります。預金も債券も広義の金融商品であり、一定期間資金を預けることで利息を得る点では共通しています。しかし、両者には根本的な違いがあります。
預金は「銀行に預ける」ものであり、元本が保証された上で利息が付与されます。一方、債券は「購入する」ものであり、市場で売買することが前提となります。そのため、債券は購入時の価格によって最終的な投資成果が異なり、場合によっては元本を回収できないリスクもあります。このように、債券は「譲渡可能」であることが特徴です。譲渡可能だからこそ、途中で換金する必要が生じた場合でも、市場で売却することで資金を回収できます。また、満期まで保有すれば、額面金額通りの払い戻しを受けることも可能です。
株式とは何が違うのか?
① 返済義務の有無
株式は企業の自己資本であり、発行企業は株主に資金を返済する義務はありません。一方、債券は発行時に定められた期日が来れば、額面金額通りに返済する義務があります。
これを投資家の視点から見ると、株式には発行企業に対して「この株を買い取ってほしい」と請求する権利はなく、売却を希望する場合は市場で取引する必要があります。一方、債券は満期を迎えると「この債券と引き換えに額面金額を支払ってほしい」と請求できる権利があり、発行者はそれを拒否することはできません。
② 価格と利回りの違い
株式は「価格」で評価されるのに対し、債券は「利回り」で示されます。例えば、「日経平均株価が360円上昇」と報道されるのに対し、債券市場では「利回りが0.2%上昇し、1.6%になった」といった形で表現されます。
③ 発行形態の違い
企業が発行する株式は通常、1社につき1銘柄ですが、債券は発行時期や条件ごとに複数の銘柄が発行されるのが一般的です。そのため、各銘柄には通し番号(銘柄回号)が付与されます。
④ 価格変動の特徴
株式の価格は、企業ごとに異なる動きをします。株式は最終的にその企業の業績を反映するため、業績が企業ごとに異なれば、株価の動きも異なるのが自然です。一方、債券の利回りは一般的に市場全体の金利動向に沿って変動します。特に、発行者の信用度が同程度であれば、利回りの動きは似た傾向を示します。
| 項目 | 債券 | 預金 | 株式 |
|---|---|---|---|
| 性質 | 借用証書のような金融商品 | 銀行に預ける資産 | 企業の自己資本 |
| 利息・配当 | 定期的な利息を受け取る | 利息を受け取る | 配当を受け取る可能性あり |
| 元本保証 | なし(市場価格により変動) | あり | なし |
| 返済義務 | あり(満期時に額面金額で返済) | あり | なし |
| 売買方法 | 市場で売買可能 | 売買不可(預金引き出しのみ) | 市場で売買可能 |
| 価格変動 | 金利動向に影響される | なし | 企業業績に影響される |
| 評価基準 | 利回りで評価 | 金利で評価 | 価格で評価 |
| 発行形態 | 条件ごとに複数の銘柄が存在 | 統一的な金融商品 | 1社につき1銘柄 |
なぜ債券は金利の指標とされるのか?
市場における代表的な金利の指標は債券の利回りです。特に、日本では毎月発行される「10年国債の利回り」が金利動向を示す重要な指標とされています。実際に、ニュースなどで「日米金利」や「米国の金利」という表現が出た場合、それは多くの場合「債券の利回り」を指しています。
債券の利回りは、預貯金金利や貸出金利、政策金利よりも先行して変動するため、これらの今後の動向を予測する重要な手がかりとなります。 特に、最も頻繁に取引されている10年物国債の利回りは、あらゆる金利の動向を先取りしています。
さらに、預貯金金利や貸出金利、政策金利は金融機関や日銀が決定するのに対して、債券の利回りは市場に参加するさまざまな投資家、例えば個人や法人、年金基金などの売買活動によって決まります。つまり、需給のバランスによって価格や利回りが自動的に決まるのです。これは株式の売買と同じで、誰かがコントロールするのではなく、市場の参加者の取引によって決まります。このため、債券の価格や利回りはその時々の経済状況を忠実に反映する指標と見なされます。しかも、国内外の投資家が参加するため、金利の動きに対する信頼性は高いと言えます。
期間10年の国債について
現在、発行されている国債の中心は10年物ですが、これには2種類があります。1つは、法人も個人も購入できる固定金利型の国債、もう1つは2003年から発行されている個人向けの変動金利型国債です。
① 10年固定金利型国債
10年固定金利型国債は原則毎月発行され、募集期間中であればいつでも購入できます。購入単位は額面基準で5万円から、利子は年に2回支払われます。発行額が多いため、換金が容易で、満期前に売却する場合は流通市場で取引されます。
② 10年変動金利型個人向け国債
2003年に初めて発行されたこの国債は、国債発行条件の多様化と個人向け投資の促進を目的としています。変動金利性、すなわち「固定金利ではなく、半年ごとに変動金利が適用されること」が最大の特徴であり、これにより、利回りや価格の変動を気にせずに保有できるため、他の多くの債券のように換金時に市場価格で売却する必要がありません。
購入後、償還時までの間に金利が上昇した場合、預金や固定金利の国債の金利が上がれば、それに合わせてクーポン金利も引き上げられます。これにより、「金利が上がっても低い利率に耐える必要がない」というリスクを回避することができます。
債券のリスク
債券投資にはいくつかのリスクがあります。利回りや価格が景気や物価などに影響を受けるため、金利変動リスクが存在します。それに加えて、債券には以下のリスクもあります。
① 流動性リスク
流動性リスクとは、債券を売買しようとしたときに、スムーズに取引できないリスクです。例えば、発行量が少なく取引が少ない債券や、特定の投資家に買い占められた債券は流動性が低くなります。これは株式にも共通するリスクです。
② 信用リスク
債券の発行者が利息の支払い義務や元本の返済義務を果たせなくなるリスクです。発行者の信用力が低い場合、発行時の利回りは高くなります。また、発行後に信用力が低下すると、債券価格は下落し、利回りは上昇します。信用リスクが高まると流動性リスクとも関連し、売却が困難になる可能性があります。
このように、債券投資には元本保証がないことや市場価格の変動リスクが伴うため、購入の際には発行者の信用力や市場の流動性を慎重に考慮する必要があります。
終わりに
債券は、その仕組みやリスクの面で一見難解に思えるかもしれません。しかし、今回の内容を通じて、債券の基本的な特性や株式や預金との違いを理解することができたのではないでしょうか。債券は、金利の変動に敏感で、発行者の信用リスクや流動性リスクも考慮する必要があります。それでも、債券市場は経済動向を反映する重要な指標であり、投資家にとっては非常に有用な金融商品であることも確かです。
債券は市場で自由に取引でき、投資家に安定した収益を提供する一方で、リスク管理が求められる資産です。今後も、金利動向や信用リスクに対する理解を深めながら、債券の運用方法を探ることが大切です。この連載を通じて、債券に対する漠然とした不安や疑問を解消し、より身近な存在として理解していただけたら嬉しいです。次回の連載では、さらに深掘りして、債券投資の実際の活用方法についてご紹介していきます。
《参考文献》
角川総一. なぜ金利が上がると債券は下がるのか. ビジネス教育出版社, 2021.