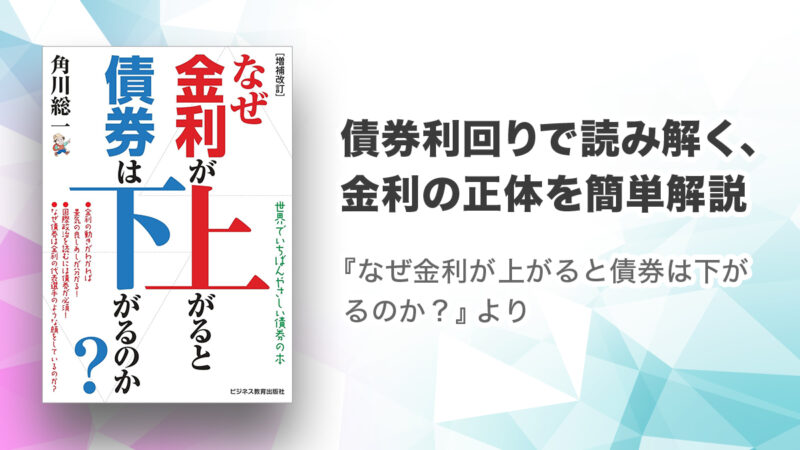「金利」という言葉を聞いたとき、多くの人は銀行預金の金利や、日本銀行の政策金利などを思い浮かべるかもしれません。でも、金利について本当に理解を深めるには、抽象的な金利概念よりも、具体的な「債券の利回り」を通して考える方が、ずっとわかりやすくなります。
たとえば「金利が下がった」というニュース。これは、実は「債券価格が上がった」ということを意味しているケースも多いのです。つまり、債券のような「金利商品」が買われると、その価格が上昇し、その結果として利回りは低下します。このように、金利と利回りの関係は、債券を通して見ることで、ぐっと身近になります。
本記事では、「債券利回りの仕組みと、その利回りを通じた金利や金融商品の収益構造の理解」について解説していきます。
今回のテーマは、「債券利回りが示す金利の動きと金融商品の収益構造」です。債券の利回りを通じて金利の変化を読み解くことで、金融市場の先行きを捉える感覚が養われます。
このテーマを理解する上で参考になる書籍として、『なぜ金利が上がると債券は下がるのか?』をご紹介します。
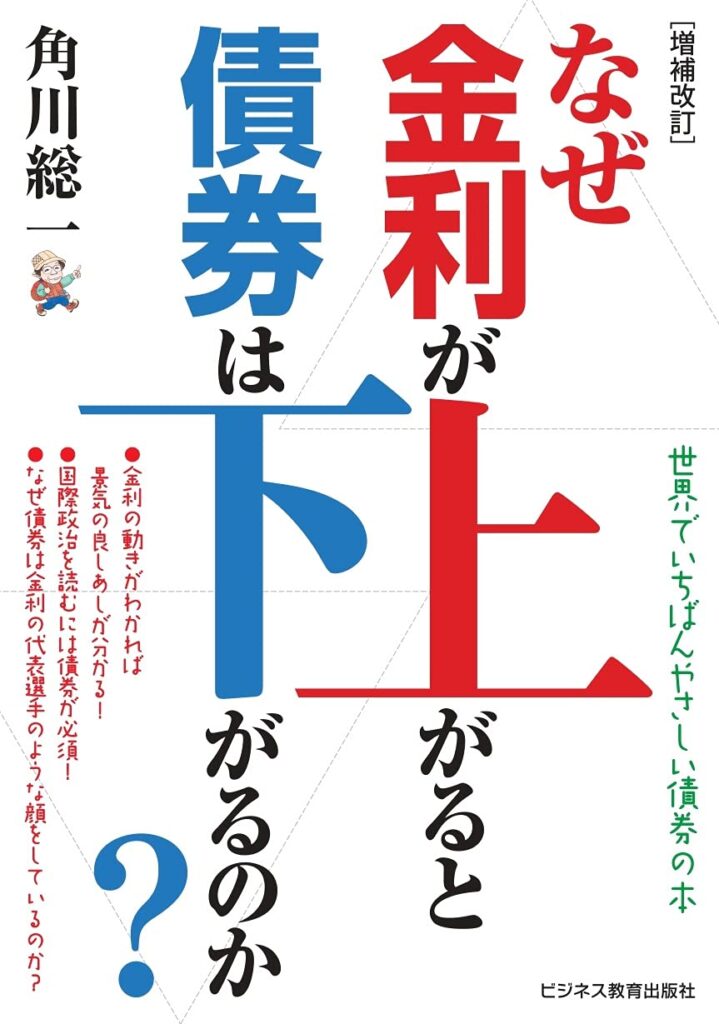
金利の変化を最も早く映すのは債券市場
実は、日本において今後の金利がどのように動いていくかを、もっとも早い段階で示してくれるのが「債券の利回り」です。金利の先行指標として機能する債券市場を見ることは、金融の動きを知るうえでとても有効な方法です。
しかし、預金やローンといった日常的な金融商品に慣れている方にとって、債券はやや難しく感じることがあるでしょう。なぜなら、債券には預金のように「利息収入(インカムゲイン)」だけでなく、「価格変動による収益(キャピタルゲイン・ロス)」も存在するからです。
この「収益の2本立て」こそが、債券という商品の本質であり、そしてそれを理解することで、他の多くの金融商品もより明確に見えてくるのです。
金融商品の収益構造を整理する
金融商品の収益は、基本的に次の2つの要素に分類できます。
インカムゲイン(利子収入)
発行条件で定められた利率(クーポン)に基づき、定期的に受け取る利子。原則としてプラスが保証され、安定性が高い。
キャピタルゲイン・ロス(値上がり益・値下がり損)
市場金利や残存期間の変化によって債券価格が上下し、償還前に売買した際や満期時の受取額の差で発生する変動的な損益。
この視点に立つと、金融商品は大きく3つのグループに分類できます。
| 分類 | 資産の例 |
|---|---|
| ① インカムゲイン型のみ | 銀行預金、郵便貯金、金銭信託 |
| ② キャピタルゲイン型のみ | 金(きん)、銀、白金、不動産(賃貸収入を除く)、債券(割引債) |
| ③ インカム+キャピタルの複合型 | 債券(利付債)、株式(配当と値上がり・値下がり)、投資信託 |
債券(利府債)はまさに③に該当します。利子による収入があり、さらに価格変動によるキャピタルゲイン・ロスもあるためです。
この収益の「安定性」という点では、インカムゲインは非常に安定しており、原則としてマイナスにはなりません。これに対し、キャピタルゲイン・ロスは非常に変動性が高く、リスクとリターンの両面で大きく振れる可能性があります。
債券の収益性を決める「3つの要素」
では、債券の利回り、つまりその収益性を決めるのは何でしょうか。以下の3つが基本です。
債券の価格(購入価格)
債券が市場で取引される価格。債券が額面より安く取引されていれば、購入時点での利回りは高くなります。
表面利率(クーポン)
債券が支払う年利。例えば、5%の表面利率を持つ債券は、額面100円に対して5円の利子を毎年支払います。このクーポンは満期まで固定されており、利子は通常、年に2回支払われます。
残存期間(満期までの年数)
債券の満期までの期間。期間が長ければ、金利の変動に対する影響が大きくなり、価格の変動もより顕著になります。
この3要素の関係性によって、債券の利回りが導き出されます。クーポンは原則固定されており、残存期間は毎日短くなるため、利回りは「価格の変動」によって日々変動するのです。
債券には「利付債」と「割引債」がある
上でも触れたように、債券には、大きく分けて2つのタイプがあります。
利付債
定期的に利息(クーポン)を支払い、満期時に元本を償還する形式の債券。安定的なインカムゲインを得ることができ、一般的な国債や社債がこれに該当する。
割引債(ゼロクーポン債)
利息の支払いは行われず、額面金額よりも低い価格で発行され、満期時に額面金額が償還される。購入時の価格と償還時の額面金額との差額が、利息に相当する役割を果たす。
それぞれの特徴を理解し、投資目的に応じて選択することが重要です。例えば、定期的な収入を重視する場合は利付債、将来の大きなキャピタルゲインを狙いたい場合は割引債が適しています。
なぜ債券は価格ではなく「利回り」で評価されるのか?
ここまでで、債券の利回りがどのように形成されるかはご理解いただけたと思います。では、なぜ債券は「価格」ではなく「利回り」で語られるのでしょうか?
たとえば、以下の2つの債券があるとします。
- A社の債券(価格98円、年利3円)
- B社の債券(価格92円、年利1円)
どちらも額面100円で3年後に満期を迎えます。一見するとAの方が利子が多くて有利に見えますが、購入価格が異なるため、単純比較では判断できません。
ここで重要なのが「利回り」。債券をどの価格で買って、どれだけの利子がもらえて、最終的に満期でどれだけ戻ってくるか。これを年利ベースで考えるのが、投資判断には欠かせないのです。
実際に、過去の金利上昇局面では、債券価格がどのように動いたのでしょうか。たとえば、アメリカでは2022年から2023年にかけて、インフレ抑制のためにFRB(連邦準備制度理事会)が急速な利上げを実施しました。政策金利は2022年3月時点の0.25%から、2023年には5%超まで上昇。その影響で、米国債をはじめとする債券価格は大きく下落しました。たとえば、2022年初頭に発行されていた10年物の米国債は、金利上昇に伴って市場価格が急落。債券の利回りは価格と反対方向に動くため、金利が上がれば利回りも上昇し、価格は下がるという関係が明確に現れました。
このように、金利の変動が債券価格に与える影響を考慮すると、「価格」だけを見て判断するのは危険です。やはり、利回りという共通の尺度で債券を評価することが、投資家にとっては合理的な判断基準になるのです。
まとめ
これまでの内容を通じて、債券投資の基本的な仕組みや収益構造を理解していただけたかと思います。金利の変動を反映する債券市場は、金融市場全体の動向を予測する上で非常に重要な役割を果たします。債券には安定した収益を得られる側面と、価格変動によるリスクも存在しますが、その特徴をよく理解することで、リスクを抑えた投資が可能になります。債券投資の本質を把握し、適切な選択を行うことで、より効果的な資産運用が実現できるでしょう。
今回の連載を通じて、第1回で債券の基礎知識と他の金融商品との違いを学び、第2回では利回りと価格の相関関係やインカムゲインとキャピタルゲインの概念を確認しました。本連載が債券を身近に感じ、債券に対する理解が深まるきっかけとなったのであれば幸いです。最後までご覧いただき、ありがとうございました。