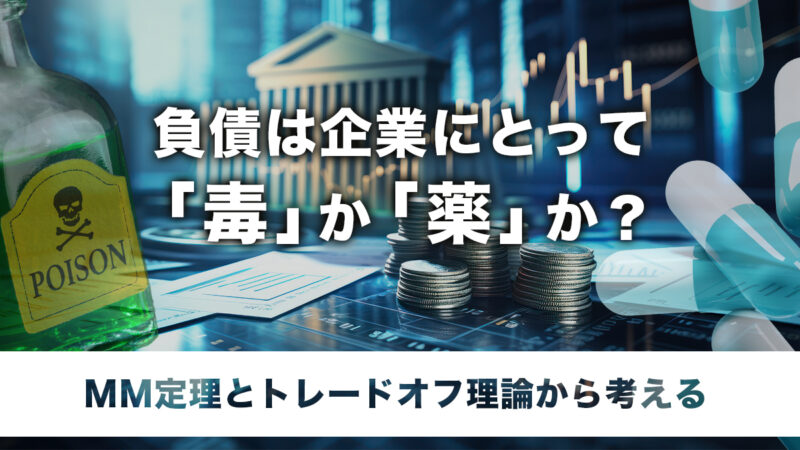「企業って、どうやってお金を集めて、どうやって使うのか?」
この問いは、企業経営の根幹にかかわるテーマであり、「コーポレートファイナンス(企業財務)」と呼ばれる分野が扱う中心的な課題のひとつです。企業は事業を展開し、成長していくために資金を必要としますが、その調達方法として大きく「株式でお金を集める」か、「借金(負債)をする」かという選択があります。どちらの手段にもメリットとデメリットがあり、これらをどのように組み合わせるかという判断が、いわゆる「資本構成」の問題です。
この資本構成が企業価値にどのような影響を与えるのか――これは企業財務において長年議論されてきた重要なテーマです。本記事では、この問いにアプローチする代表的な理論である「MM定理」と「トレードオフ理論」の考え方を比較しながら、「負債による節税効果」が企業価値にどのように影響するかについても解説していきます。
MM定理:資本構成は関係ないという大胆な主張
まず、MM定理(Modigliani-Miller Theorem)は、1958年に経済学者モディリアーニとミラーによって提唱された理論です。彼らの主張はとてもシンプルで、「企業の価値は、資本構成に関係なく決まる」というものです。つまり、企業がどれだけ借金をしていようと、株で資金を集めていようと、その企業の本質的な価値には関係ない、ということです。
なぜそんなことが言えるのでしょうか? それはMM定理がいくつかの現実離れした仮定をおいているからです。具体的には以下のようなものがあります。
- 法人税などの税金が存在しない
- 倒産のリスクがない
- 投資家はすべての情報を持っていて、合理的に判断する
- 資金を借りるコストは誰でも同じ
このような、いわゆる「完全市場」を前提にすれば、資本構成を変えても企業価値に変化はないとMM定理は結論づけます。
なお、モディリアーニ=ミラー自身もその後の1963年の論文で、法人税の存在を考慮したモデル(いわゆる「MM理論の第二命題」)を発表しており、負債による節税効果の可能性についても言及しています。
ただし、実際の企業活動においては、法人税や利子の損金算入といった税制上の影響、投資家と経営者の間にある情報格差、資金調達に伴うコスト、そして負債が増えることによる財務リスクなど、さまざまな要素が企業価値に影響を及ぼします。そのため、MM定理は、理論上は成立していても、現実の世界では必ずしもそのまま当てはまるとは限りません。こうした背景から、MM定理はしばしば「理論的には正しいが、現実には通用しない」と言われるのです。
税金がある世界では、負債にメリットがある?
ここで注目したいのが、負債の節税効果です。企業が銀行などから借金をすると、利子を支払う必要がありますが、この利子は会計上「費用」として扱われます。その結果、企業の利益が少なく見えるようになり、課税所得が減って法人税の額も小さくなるのです。
たとえば、企業が1,000万円の借金に対して年間50万円の利子を支払っていて、法人税率が30%だったとしましょう。この場合、50万円の利子によって、15万円分の税金が節約できることになります。このように、負債を活用することで企業の手元に残るお金が増えるため、企業の価値が高まる要因となるのです。
とはいえ、無制限に借金を増やすのは現実的ではありません。次に、そこにブレーキをかける理論を紹介します。
トレードオフ理論:得と損のバランスで最適を探す
トレードオフ理論(Trade-off Theory)は、MM定理に現実的な要素を加味した考え方です。企業が負債を使うと、たしかに節税効果が得られて企業価値は上がります。しかし、借金が増えすぎると、返済が難しくなり、最悪の場合は倒産するリスクも高まります。
この倒産リスクが現実になると、以下のようなコスト(=財務危機コスト)が発生します。
- 破産手続きや資産売却にかかる法務費用が発生する
- 将来の利益機会を失う
- 信用格付けが低下し、資金調達が難しくなる
- 取引先や顧客からの信頼を失う
- 従業員の士気が低下する
例えば、2008年のリーマン・ショックでは、米大手投資銀行のリーマン・ブラザーズが過度なレバレッジ(借入)を抱えたまま不動産バブルの崩壊に直面し、破綻しました。この破綻は、法務費用や資産売却による損失だけでなく、世界中の金融市場に信用不安をもたらし、他企業への連鎖的な悪影響を引き起こしました。
このような負債による財務危機コストが一定以上に大きくなると、節税によるメリットを打ち消してしまいます。そこで、トレードオフ理論ではこう考えます。
「節税によるメリット(プラス)と財務危機コスト(マイナス)のバランスが取れた点で、企業価値が最大になる。」
このバランスが取れた資本構成のことを「最適資本構成(optimal capital structure)」と呼びます。最適資本構成とは、負債と自己資本の組み合わせが、企業価値を最大化するように設計された資本のバランスを意味します。
| 観点 | MM定理 | トレードオフ理論 |
|---|---|---|
| 基本的な考え方 | 資本構成(負債と株式の比率)は企業価値に影響しない | 負債のメリット(節税)とデメリット(リスク)をバランスさせたとき企業価値が最大になる |
| 前提条件 | 完全市場(税金なし、倒産リスクなし、情報完全、借入費用一定) | 現実的な市場(税制、倒産リスク、資金調達コストなどを考慮) |
| 企業価値への影響 | 負債比率を変えても企業価値は不変 | 適切な負債水準は企業価値を高める |
| 負債のメリット | 考慮されない | 利子の損金算入による節税効果がある |
| 負債のデメリット | 考慮されない | 倒産リスクや財務危機コストが発生 |
| 理論の使われ方 | 理論的なベースモデルとして重要 | 現実の企業財務に応用されやすい |
ステークホルダーの視点も忘れずに
最近では、株主だけでなく、従業員や取引先など「ステークホルダー(利害関係者)」の福祉も企業価値に影響を与えると考えられています。とくに従業員にとって、企業の倒産は生活に直結する大問題です。こうした視点を重視する企業ほど、リスクをできるだけ避けようとする傾向があり、あえて負債比率を低く保つ場合もあります。
上記を踏まえて
負債は企業にとって、単なる資金調達の手段にとどまりません。それは、成長の可能性を広げるレバレッジであると同時に、慎重な対応を求められるリスク要因でもあります。MM定理やトレードオフ理論が示すように、理論的な枠組みは資本構成の意思決定を考えるうえで大切な指針になりますが、そこには現実の複雑さまでは描ききれません。企業は、それぞれが置かれた環境やステークホルダーとの関係性のなかで、自らの価値観や優先順位に沿った選択を迫られます。
その意味で、資本構成の問題は、財務のテクニカルな議論を超えて、企業そのものの姿勢や価値観に関わるテーマだと言えるでしょう。成長か、安定か。リスクを取るか、守りを固めるか。その選択には、正解も公式もありません。だからこそ、理論に学びながらも、自社にとっての「最適」とは何かを問い続ける姿勢が求められているのです。